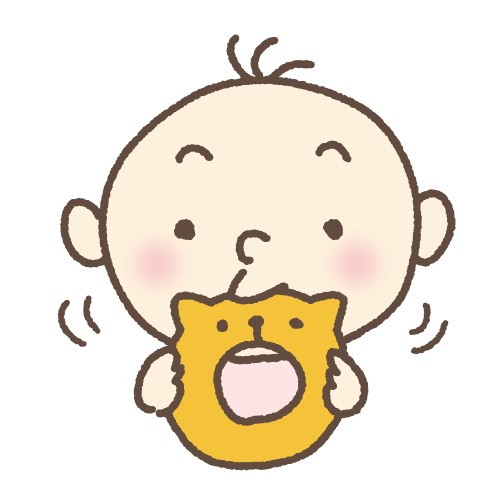小さなお子様が指しゃぶりをしている姿はかわいらしく、赤ちゃんの頃からの癖として自然な行動の一つです。しかし、指しゃぶりが長く続くと歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすことがあります。「いつまでなら大丈夫なの?」「どうやってやめさせればいいの?」と不安に感じている親御様も多いのではないでしょうか。
本記事では、指しゃぶりが歯並びに及ぼす影響や、放置してよい年齢の目安、指しゃぶりをやめさせる方法について詳しく解説します。お子様の健やかな成長をサポートするために、ぜひ参考にしてください。
▼指しゃぶりが歯並びを悪くするメカニズム
指しゃぶりが長く続くと、歯並びや噛み合わせにさまざまな影響を及ぼします。その主な原因は、指が歯や歯茎に継続的に圧力をかけることによるものです。
- 出っ歯(上顎前突)になる
指しゃぶりをしていると、親指が上の前歯を前方に押し出し、出っ歯(上顎前突)になる可能性が高くなります。特に、強く吸う癖があるお子様は、前歯が前方に突出し、口が閉じにくくなることがあります。
- 開咬(かいこう)になる
指しゃぶりを長期間続けると、上の前歯と下の前歯の間に隙間ができる「開咬(かいこう)」と呼ばれる状態になることがあります。開咬になると、奥歯は噛み合っていても前歯で食べ物を噛み切ることが難しくなります。
- 受け口(反対咬合)を引き起こすことも
まれに、指しゃぶりの影響で下の顎が前に出てしまい、受け口(反対咬合)になることもあります。これは、顎の発達に悪影響を及ぼし、将来的に矯正治療が必要になるケースもあります。
- 顎の発育に影響を及ぼす
指しゃぶりが習慣化すると、上顎の成長に偏りが生じ、顎の形が狭くなることがあります。これにより、歯が正しく並ぶスペースが不足し、歯並びが乱れる原因となります。
▼指しゃぶりは何歳まで放置してもいい?
指しゃぶりは、赤ちゃんの頃は生理的なものですが、3歳以降も続く場合は注意が必要です。
- 2歳までは自然な行動
2歳頃までの指しゃぶりは、赤ちゃんの本能的な行動であり、発達の一環とされています。この時期は無理にやめさせる必要はありません。

- 3歳以降は要注意
3歳を過ぎても指しゃぶりが続く場合は、習慣化している可能性があります。この頃から指しゃぶりが原因で歯並びに影響を及ぼし始めるため、様子を見ながら対策を考えましょう。
- 5歳までにはやめさせるのが理想
永久歯が生え始める5歳頃までには、指しゃぶりをやめさせることが理想的です。それ以降も続けていると、歯並びの乱れや顎の成長に悪影響を及ぼし、矯正治療が必要になることもあります。
▼指しゃぶりをやめさせる方法
子供の指しゃぶりは、まずご自宅での取り組みでやめさせるのが理想です。それでも難しい場合は、歯科医院のサポートを受けましょう。
【自宅での対処法】
◎指しゃぶりの原因を探る
お子様が指しゃぶりをする理由には、眠気、不安、退屈などが関係しています。安心感を求めている場合は、スキンシップを増やし、環境を整えることが大切です。
◎手を使う遊びを増やす
指しゃぶりを忘れるように、粘土遊びやブロック遊びなど、手を使う遊びを取り入れると良いでしょう。
◎「やめなさい」と怒らない
無理にやめさせようとすると、かえってストレスになり、逆効果になることがあります。優しく声をかけながら、少しずつ習慣を変えていきましょう。
◎寝る前の工夫
寝る前に指しゃぶりをするお子様には、好きなぬいぐるみを持たせたり、絵本を読んであげたりすると、指しゃぶりをする時間が減ることがあります。
【歯科医院での対処法】
◎歯医者さんに相談をする
指しゃぶりがなかなかやめられない場合は、歯科医師に相談するのも一つの方法です。歯並びに影響が出始めているかどうかをチェックし、適切なアドバイスを受けられます。
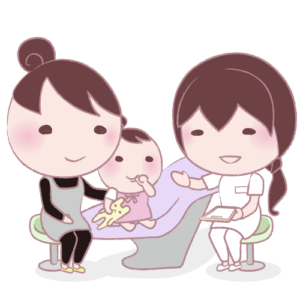
◎マウスピースの活用
必要に応じて、指しゃぶりを防ぐためのマウスピースを使用することもあります。特に、5歳を過ぎても指しゃぶりが続く場合には、矯正治療の一環としてマウスピースが有効な場合があります。
◎行動療法の指導
指しゃぶりを防ぐための具体的な方法や、保護者様向けの指導を行うこともあります。
▼まとめ
指しゃぶりは、赤ちゃんのうちは自然な行動ですが、3歳を過ぎると歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があります。特に、5歳を過ぎても続く場合は、早めに対策を取ることが大切です。
ご家庭では、お子様が安心できる環境を作り、手を使う遊びを増やすなどの工夫をしてみましょう。無理にやめさせるのではなく、少しずつ自然に減らしていくことがポイントです。それでも指しゃぶりが続く場合や、歯並びに影響が出始めていると感じた場合は、歯科医院に相談することをおすすめします。当院でも、お子様の成長に合わせた適切なアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。